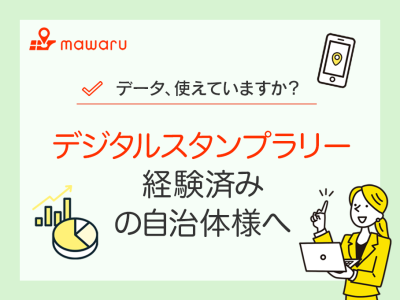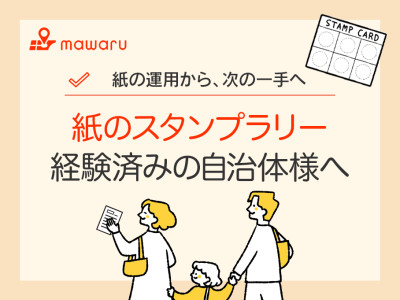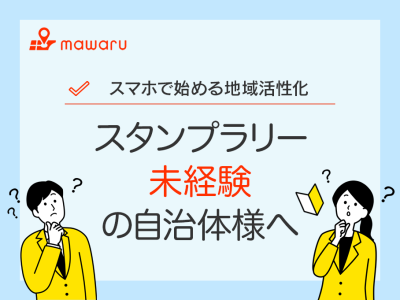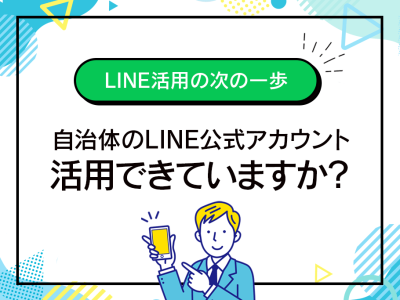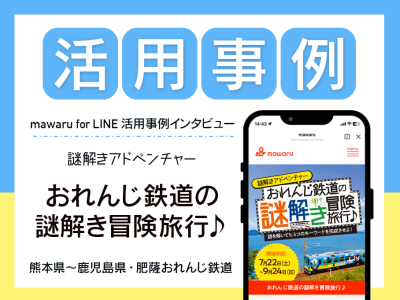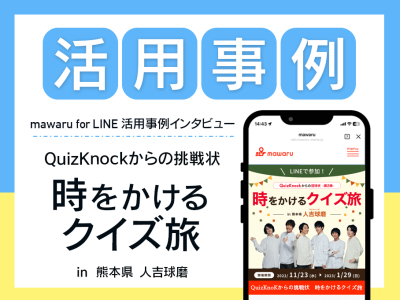【観光地がなくても大丈夫!】広域連携で拓くスタンプラリーのチカラ

「うちには有名な観光地がない」「魅力的なスポットが少なくて、スタンプラリーなんて無理だ」
そう感じ、企画を諦めてしまう自治体のご担当者様は少なくありません。
しかし、本当にそうでしょうか?
実は、あなたの地域が持つ「隠れた魅力」を最大限に引き出し、参加者を惹きつける秘策があります。
それが、一過性で終わらないキャンペーンを実現する「広域連携」によるデジタルスタンプラリーです。
今回は、「目玉がない」という課題を逆手に取り、広域連携による新たな可能性をご紹介します。
目次
なぜ「魅力がない」と感じてしまうのか?自治体が抱える本音
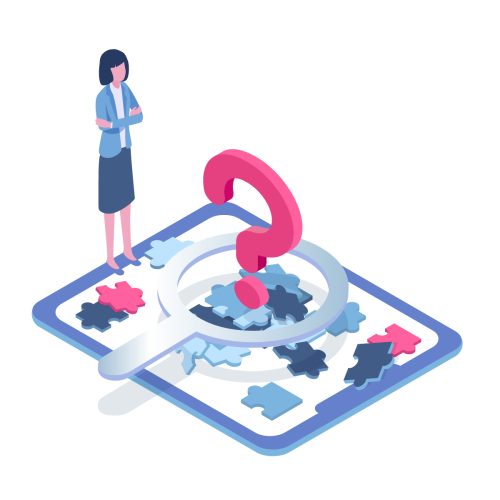
デジタルスタンプラリーは地域を盛り上げ、交流人口を増やす有効な手段です。しかし、企画担当者様からはこんな声が聞かれます。
- 「シンボル的な観光地がない」
- 「自然も歴史的建造物もない」
- 「予算・人材が限られ、企画が難しい」
- 「一部に人が集中し、広がりがない」
これらは多くの自治体が抱える共通の課題です。しかし、この「魅力がない」という認識こそが、実は大きなチャンスを秘めています。
解決策は「広域連携」!地域の新たな魅力を引き出す秘訣

個々の自治体だけでは「目玉がない」と感じる場所でも、複数の地域が連携すれば、点と点が繋がり、面となって、これまでにない大きな魅力を創出できます。
「広域連携」デジタルスタンプラリーの主なメリットは以下の通りです。
< 分散魅力を繋ぎ周遊ルートを創出 >
点在名所をテーマで結び、広域周遊促進、滞在・消費拡大へ繋げます。
< 新たな観光資源の発見 >
「地元しか知らない」穴場を発掘し、外部視点で魅力を磨き上げます。
< 交流・関係人口の拡大 >
広域周遊で滞在・消費を促し、中長期的な関係人口創出に貢献します。
< 予算・リソース共有と効率化 >
単独困難な大規模企画も共有で実現。運営負担を軽減し、効率的なキャンペーン実施が可能に。
< データ活用と継続関係構築 >
参加者データを蓄積・分析。LINEでキャンペーン後も情報発信し、次施策やリピーター創出に繋げます。
【具体的なアイデア】観光に頼らない広域スタンプラリー
「目玉」がなくても実践できる、広域連携スタンプラリーの企画アイデアをご紹介します。
① ストーリー性で繋ぐ「テーマ型周遊」
有名な観光地がなくても、地域に共通する「テーマ」を見つけ出しましょう。
- ご当地グルメ横断ラリー:複数の地域の「B級グルメ」や特産品料理を巡る。
- 歴史・文化探訪ラリー:共通の歴史上の人物ゆかりの地、昔の街道などを巡る。
- 季節限定の自然・風景ラリー:桜並木、清流、紅葉スポットなどを巡る。
- アニメ・漫画・映画の聖地巡礼:作品の舞台となった地域を横断する(もし該当する作品があれば)
② 「移動手段」を主役にしたラリー
特定の観光地だけでなく、移動そのものを目的としたスタンプラリーも有効です。
- 路線バス・鉄道沿線ラリー:特定路線のバス停や駅周辺の見どころ・お店を巡る。
- 道の駅・産直市巡りラリー:各地域の道の駅や産直市を巡り、特産品に触れる。
③ 住民も巻き込む「まちの発見」ラリー
- 地元住民おすすめスポット巡り:住民募集で「隠れた名所」「とっておきの店」を、スタンプスポットに。
- 防災・減災意識向上ラリー:各地の避難所や防災施設などを巡り、地域を「知る」事で防災意識を高める。
【成功事例】南九州3県を繋ぐデジタルスタンプラリー

広域連携によって大きな可能性に変わることを証明したのが、南九州3県(熊本県・宮崎県・鹿児島県)で2年連続で実施された「ぐるーーーっと南九州3県デジタルスタンプラリー」です。
この企画は、南九州広域観光ルート連絡協議会が、コロナ禍での教育旅行低迷を受け、個人誘客・隣県周遊促進へ方針転換し、過去実績のあるMARUKUのデジタルスタンプラリーを提案したのがきっかけ。宮崎県の横山氏も「単県より影響力や発信力が大きくなる」と広域連携に期待しました。
【 なぜ「mawaru for LINE」が選ばれたのか?〜アプリ不要で「一過性」にしない〜 】
数あるサービスから「mawaru for LINE」が選ばれた最大の理由は、その「手軽さ」と「継続性」です。
熊本県の藤澤氏は「独自アプリはハードルが高いが、スマホ利用者の大半が使うLINEなら多くの参加が期待できる。終了後もLINEで情報発信が可能な点も決め手」と語ります。宮崎県の横山氏も「ブラウザ型は不親切。LINE上で全て完結する『mawaru for LINE』は秀でている」と評価。これにより「一過性のキャンペーンでは終わらない」(熊本県・柳邊氏)プロモーションが実現しました。
【 主催者・参加者双方に嬉しいメリット〜運営負担軽減とデータ活用の両立〜 】
デジタル化により、運営側の負担は大幅に軽減。台紙・スタンプ設置、応募用紙回収・入力の手間が不要となり、準備の迅速化と効率化を実現しました。横山氏からは「スタンプ台の設置の必要が無いことなど、施設側の負担もないと好評だった」との声も。参加者の行動データも自動蓄積され、プロモーションへの活用を促進します。
【 予想以上の成果と、未来への確かな手応え 】
2年連続実施の結果、累計3,471人ものLINE友だち登録を達成。全90スポットを予想を超える4名がコンプリートするなど、大きな周遊効果を見せました。アンケートでは「若い層だけでなく40代、50代の参加者が多かった」(鹿児島県・熊野氏)という新たな発見もあり、詳細データを迅速に把握できる強みを実感。MARUKUの一括広報支援も間接的な効果に繋がりました。
【 MARUKUの伴走支援と継続への意欲 】
MARUKUの「私たちにはない知見」(鹿児島県・熊野氏)による企画・運営、応募要件設定までの伴走支援は「とても心強かった」と高く評価されています。
今後も「成長、進化させたい」(宮崎県・横山氏)という継続への意欲が示され、熊本県の藤澤氏からは「LINE IDと紐づいた情報収集や個別アンケートで参加者の声を集め、より満足度の高い観光地域づくりに繋げたい」というデータ活用を通じた展望が語られました。鹿児島県の熊野氏は、デジタルスタンプラリーを「人が集まりすぎるのを防ぎ、観光客を分散させながら楽しめる、現代ニーズに即したツール」と結論づけています。
▼ さらに詳しい事例はこちら
【mawaru for LINE活用事例インタビュー#1】 熊本県×鹿児島県×宮崎県
▼ 参加者のリアルな声をもっと知りたいですか?
「また参加したい」と思われるデジタルスタンプラリーの秘訣を、320名への独自アンケート結果から徹底解説しています。
参加者の生の声から紐解く成功の秘訣はこちら
まとめ|広域連携は「ない」を「ある」に変える力
「地域には何もない」という思い込みも、広域連携で「可能性の宝庫」に変わります。
点と点を繋ぎ、面で広げることで、新たな周遊体験と地域全体の活性化に繋がるのです。
デジタルスタンプラリーは単なるツールではありません。
LINE活用により参加者と継続的につながり、データを蓄積・分析することで、地域の新たな魅力発見や、未来を見据えたまちづくり戦略に繋がる示唆を与えてくれます。まさに「一過性で終わらないキャンペーン」を実現する鍵です。
株式会社MARUKUでは、各自治体様の課題に合わせ、最適なデジタルスタンプラリーの企画・開発をサポートしています。「広域連携」にご興味がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。貴自治体と周辺地域の新たな可能性を、共に探していきましょう。
弊社の「mawaru for LINEスタンプラリー」について、さらに詳しい情報は、以下のリンクよりご覧いただけます。